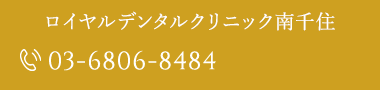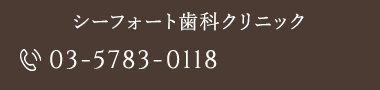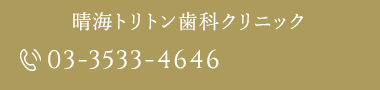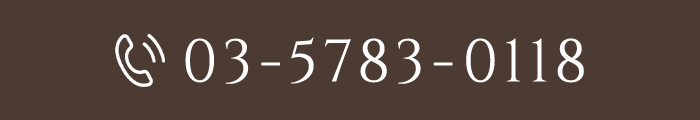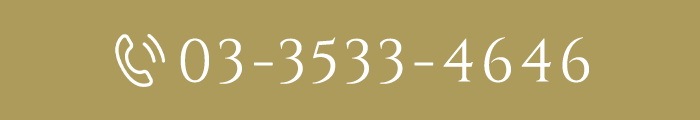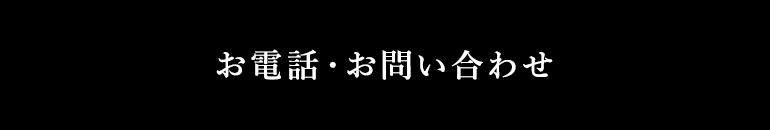すきっ歯は“削らず”治せる?マウスピース矯正の期間・費用・失敗しない選び方
すきっ歯は見た目だけじゃない──“機能面”にも影響を与える理由とは?

笑ったときの印象が変わる──“すきっ歯”が与える意外な見た目の影響
すきっ歯は、笑ったときや会話中に最も目につきやすい部位にあるため、清潔感や若々しさ、そして全体的な印象に大きく影響します。 前歯のわずかな隙間でも、「歯並びが悪い」「お手入れが十分ではない」という印象を与えてしまうことがあります。 特に接客業や人前に出る機会の多い方にとっては、口元への意識が高くなるポイントです。
また、歯の隙間は光の反射の仕方にも影響し、歯全体が暗く見えたり、影が生まれて口元が不自然に見えることもあります。 さらに、隙間があることで歯と歯の位置関係が乱れ、全体の歯列バランスが崩れて見える場合もあります。 こうした視覚的な印象の変化は、本人の表情や自信にも少なからず影響を及ぼします。
しかし、歯を削らずに整える治療法が進歩した今では、すきっ歯を自然な形で改善し、清潔で調和のとれた印象を取り戻すことができます。 見た目の印象を整えることは単なる「美容」ではなく、表情の明るさや人とのコミュニケーションを前向きにする一歩にもなります。
- 印象面:清潔感・若々しさ・調和のとれた口元
- 光の反射:隙間により暗く見えたり影ができやすい
- 表情面:自信や笑顔の自然さにも影響
実は発音や噛み合わせにも関係?放置による機能面のリスク
すきっ歯は審美面だけでなく、発音や咀嚼(そしゃく)といった機能面にも影響を与えます。 前歯に隙間があることで空気が漏れやすくなり、「サ行」「タ行」「ス」「ツ」などが聞き取りにくくなることがあります。 これは特に英語の発音を含む会話やアナウンス業務を行う方にとって、気づかれにくい悩みのひとつです。
また、隙間の存在は噛み合わせのバランスを崩し、特定の歯にだけ負担が集中する原因にもなります。 こうした状態が続くと、歯の摩耗や歯根への負担が進み、最終的には歯周組織の炎症や歯の動揺を引き起こすこともあります。 さらに、食べ物のカスが詰まりやすくなるため、虫歯や口臭の発生リスクも高まります。
すきっ歯は「見た目の悩み」として軽く考えられがちですが、実は噛む・話す・守るという歯の基本機能に関わる重要なサインです。 発音や咀嚼時に違和感を感じたら、早めに歯科医師へ相談し、原因を正確に見極めることが将来的なトラブル防止につながります。
- 発音:空気漏れによる発音の不明瞭化
- 噛み合わせ:負担の偏りで摩耗・炎症リスク
- 清掃性:食片停滞で虫歯・口臭の原因に
早めに整えることが将来のトラブルを防ぐ理由
すきっ歯を放置すると、年齢とともに歯列が少しずつ動き、隙間が広がることがあります。 歯ぐきが下がったり、歯槽骨(しそうこつ)が吸収されることで支えが弱まり、結果として噛み合わせが変化することもあります。 噛み合わせがずれると、顎関節(がくかんせつ)に余計な負担がかかり、顎の音や痛み、肩こりなどを引き起こすことも少なくありません。
また、隙間部分にはプラークや歯石が付着しやすく、歯周病や虫歯のリスクを高めます。 特に、前歯部は清掃が難しいため、見た目が良くても内部で炎症が進行するケースもあります。
近年は、歯を削らずに行うマウスピース矯正によって、軽度のすきっ歯であれば短期間で改善できるケースも増えています。 透明で目立たず、日常生活に支障をきたしにくいことから、社会人にも取り入れやすい方法です。
見た目の印象だけでなく、歯の寿命や咀嚼機能を守るためにも、違和感を感じた時点での早期受診が大切です。 すきっ歯の改善は「美しさのため」だけでなく、噛める・話せる・守れる口腔機能を長く維持するための第一歩です。
- 歯列変化:年齢とともに隙間が広がるリスク
- 顎関節負担:ズレによる顎や肩への影響
- マウスピース矯正:非侵襲的で自然に改善
あなたのすきっ歯はどのタイプ?原因を知れば正しい治療法が見えてくる

歯と歯のサイズ不調和が原因の“生まれつきタイプ”
歯の大きさや形のバランスが生まれつき合っていないことで、歯と歯の間にすき間ができるタイプです。 特に、上の前歯が小さい「矮小歯(わいしょうし)」や、歯列全体の幅に対して歯が小さいケースでは、自然にすきっ歯が生じます。 こうした場合は、歯や骨の位置関係に大きな問題がないため、歯を削らずにすき間を閉じるマウスピース矯正が有効です。 歯の位置をミリ単位で微調整することで、見た目のバランスを整え、噛み合わせも自然な形に誘導できます。
治療後は歯のサイズ感と唇のラインが整い、口元全体が調和します。 なお、インプラントや補綴を検討するのは、欠損歯や極端な不調和がある場合に限られます。
- 原因:歯の大きさ・形のアンバランス
- 特徴:見た目以外の機能的問題は少ない
- 治療例:マウスピース矯正で自然に整える
舌癖・口呼吸など、後天的にすきっ歯をつくる“機能性タイプ”
舌で前歯を押す癖(舌突出癖)や、口呼吸の習慣があると、前歯に外向きの力が長期的に加わり、少しずつ歯が前方へ広がってすきっ歯が生じることがあります。 こうしたタイプでは、単に歯を動かす矯正だけでは再発のリスクがあり、舌の位置や呼吸の習慣を改善するアプローチが欠かせません。
マウスピース矯正は舌の位置を意識しやすく、日常の癖を修正する助けにもなります。 治療後は咀嚼や発音が安定しやすくなり、再発を防ぐための保定期間中の舌の訓練も重要です。 こうした生活習慣の改善を並行することで、より長く美しい歯並びを維持できます。
- 原因:舌で前歯を押す・口呼吸などの習慣
- 治療法:矯正+舌・呼吸トレーニング
- 再発防止:保定期間中の舌訓練が重要
骨格や歯列幅が関係する“構造的タイプ”と診断の重要性
上顎骨や歯槽骨の幅が広すぎる、または歯列の形態が原因で隙間が生じるケースは「構造的タイプ」に分類されます。 この場合、単純な歯の移動だけでは改善が難しいこともあり、治療計画の立案には精密な診断が欠かせません。
歯科用CTやデジタルスキャンを活用して骨の厚みや歯根の角度を分析し、 マウスピース矯正で対応できるか、または部分的に補綴治療を組み合わせるかを判断します。 見た目だけで判断するのは難しいため、骨格や筋肉、歯列全体のバランスを総合的に評価することが大切です。
まずはカウンセリングで自身のすきっ歯の「原因タイプ」を明確に知ることが、失敗しない治療選択の第一歩となります。
削らず治す時代へ──マウスピース矯正で“すき間を閉じる”仕組み

歯を削らずに整える──マウスピース矯正の基本メカニズム
マウスピース矯正は、歯を削らずに「動かして整える」ことを目的とした治療法です。歯列全体を強く引っ張るのではなく、ひとつひとつの歯に計算された弱い力を加えることで、少しずつ自然な位置へ移動させていきます。専用ソフトで作られるマウスピース(アライナー)は、1枚ごとに0.2〜0.3mm単位で歯を動かすよう設計され、患者様は一定期間ごとに新しいものへ交換します。
この“段階的に動かす”仕組みによって、歯質を削ることなく形態を保ちながら歯列を整えられる点が特徴です。治療による歯へのダメージや再治療のリスクを抑えられ、将来的な健康維持にもつながります。また、力の方向や移動量をデジタル上で細かく調整できるため、軽度のすきっ歯やねじれ、前突などにも柔軟に対応できます。
透明で目立たない!快適に続けられるマウスピースの特徴
マウスピース矯正の大きな特徴は、その“快適さ”です。以下のようなポイントが、多くの患者様に支持されています。
- 透明な医療用樹脂で作られており、装着中もほとんど目立たない
- 金属不使用のため違和感や金属アレルギーの心配が少ない
- 取り外し可能で、食事・歯みがきも普段どおりできる
- 表面が滑らかで、頬や舌を傷つけにくく発音も自然
- 仕事中や人前でも自然な印象を保ちやすい
見た目・衛生・快適性を両立し、長期にわたる治療も前向きに続けやすいのがマウスピース矯正の魅力です。
ワイヤー矯正・ラミネートベニアとの違いを徹底比較
ワイヤー矯正は幅広い症例に対応できる反面、装置が目立ちやすく、食事制限や清掃の難しさがデメリットとされます。ラミネートベニアは短期間で見た目を改善できる方法ですが、歯の表面を薄く削る必要があり、歯質の保存という点では制約があります。
一方、マウスピース矯正は「削らずに動かす」という点で、自然な歯を守りながら整える保存的な治療法です。軽度のすきっ歯や歯並びのズレに対して、咀嚼機能と見た目の両立を図ることができます。治療後も自分の歯を活かしながらメンテナンスを続けることで、長期的に安定した口腔環境を保つことが可能です。
すきっ歯矯正の期間はどのくらい?症状別に見るリアルな目安

前歯だけの軽度すきっ歯──数か月で整うケースも
前歯のすき間がわずかで、歯並び全体に大きなズレがない場合は、マウスピース矯正で3〜6か月ほどの短期間で整うことがあります。歯を削らず、マウスピースを段階的に交換しながら少しずつ歯を動かすため、痛みや違和感も少ないのが特徴です。治療期間を左右するのは装着時間の遵守です。
1日20時間以上しっかり装着できれば、計画どおりに歯が動きやすくなります。加えて、交換周期(7〜14日)を守ること、来院時のチェックで微調整を重ねることがスムーズな進行につながります。
リテーナーでの保定期間も含めると通院はやや長く感じますが、歯質を守りながら見た目と機能の両立を目指せる点が利点です。早めの相談は適応判定と計画立案に役立ちます。
上下のバランスを整える中等度タイプの治療期間
すきっ歯が上下の歯列に広がっている場合や、噛み合わせのズレを伴うケースでは、治療期間は6〜10か月程度が目安になります。上下の歯が均等に動くように調整し、咬合のバランスを取りながらすき間を閉じていきます。
このタイプでは、単に見た目を整えるだけでなく噛む機能(咀嚼)を安定させることが重要です。治療中は6〜8週ごとの経過観察で咬合接触や歯の移動方向を確認し、必要に応じて計画を見直します。
生活リズムに合わせた装着管理、ブラッシングや清掃補助具の活用も、予定通りの進行に影響します。保定開始後は後戻りを抑えるため、就寝時のリテーナー使用と定期メンテナンスの継続が推奨されます。
ねじれや傾きがある複合タイプ──時間をかけて精密に動かすケース
歯のねじれや傾きがある場合は、単純にすき間を閉じるだけでなく、歯軸を整える工程が必要となります。こうした複合タイプでは治療期間が10〜14か月程度かかることもあります。
精密な三次元的移動を要するため、途中経過で追加のマウスピースを作成して軌道修正(リファインメント)を行うことがあります。長期治療ほど、噛み合わせや舌の位置などの機能面も重視され、発音や咀嚼の違和感を避けるための段階的調整が有効です。
装着時間の管理に加え、舌癖や口呼吸の改善、歯周組織の健康管理が仕上がりと安定性に影響します。焦らず計画に沿って進めることが、後戻りを抑えた落ち着いた結果につながります。
マウスピース矯正の費用相場と支払い方法──無理なく始めるために

部分矯正と全体矯正の費用レンジを比較
マウスピース矯正の費用は、治療範囲や難易度によって大きく異なります。前歯だけを対象にした部分矯正であれば、おおよそ20〜40万円が一般的な相場です。一方で、上下全体の歯並びを動かす全体矯正では80〜100万円前後が目安となります。部分矯正は歯の移動距離が短く、治療期間も比較的短いため、費用を抑えつつ見た目の印象を整えたい方に適しています。
ただし、見た目を整えるだけでなく、噛み合わせを含めた全体のバランスを改善する必要がある場合は、全体矯正が選択されることもあります。歯の移動方向や咬合状態の診断には専門的な分析が必要であり、単純な価格比較だけでは判断できません。費用は治療の「規模」ではなく、「必要な精度と範囲」によって決まるため、まずは現状を正確に把握することが大切です。
ラミネートベニアなど他の治療法とのコスト比較
すきっ歯の改善には、マウスピース矯正のほかにラミネートベニアなどの審美治療も選択肢に入ります。ベニアは短期間で見た目を整えられますが、歯の表面を薄く削る必要があり、1本あたり10〜15万円が一般的です。複数本に適用する場合、結果的に矯正より高額になるケースもあります。
一方、マウスピース矯正は歯を削らず、自然な歯の位置関係を活かして治すため、再治療のリスクが低く、長期的な歯質保存にもつながります。短期的な見た目の変化だけでなく、「治療後の安定性」「将来の修復リスク」なども踏まえて総合的に比較することが重要です。治療を始める前に、それぞれの方法のメリット・デメリットを歯科医と一緒に整理しておくと安心です。
医療ローン・分割払いで無理なく通える支払いプラン
マウスピース矯正は自費治療のため、費用面を不安に感じる方も少なくありません。多くの歯科医院では、医療ローンや院内分割制度を導入しており、月々1〜2万円前後の分割で無理なく始められるケースもあります(内容は医院によって異なります)。金利が抑えられ、頭金不要で利用できる場合も多く、初期負担を軽減しながら計画的に治療を進められます。
また、医院によっては矯正前の診断料や保定装置の費用が別途発生することがあるため、見積もりの段階で「総額」を確認することが大切です。費用の透明性を重視する医院では、分割回数や金利条件も明確に提示してくれるため、安心して治療に踏み出しやすくなります。カウンセリング時には、治療内容だけでなく支払い方法の相談も遠慮なく行い、自分に合った無理のないプランを一緒に検討しましょう。
削らず整うまでの流れ──マウスピース矯正のステップ解説

初診〜カウンセリング:歯列スキャンで原因を可視化
初診では、まず口腔内を3Dスキャナー(iTeroなど)で撮影し、歯列や咬合の状態をデジタルで再現します。これにより、歯の位置関係や歯列幅、ねじれの程度、噛み合わせのズレといった構造的な要因を細かく把握できます。また、舌の動きや口呼吸など、歯並びに影響を与える機能的な要素も同時に確認します。
診断結果をもとに、「どの歯をどの程度動かすか」「どのくらいの期間で整うか」といった全体像を説明し、治療のゴールを共有します。治療計画や費用だけでなく、ライフスタイルや職業、装着時間の確保なども考慮してプランを立てることが大切です。こうした丁寧なカウンセリングを通じて、患者様が安心して治療を始められる環境を整えます。
治療計画〜マウスピース作製:オーダーメイド設計の重要性
カウンセリング後は、スキャンデータをもとに歯の動きをコンピュータ上でシミュレーションします。マウスピース矯正では、1枚ごとのマウスピースが「どの歯を」「どの方向に」「どのくらいの力で」動かすかを精密に設計します。削らずに整えるという前提のもと、歯や骨に無理のない範囲で、適切な移動量を設定することが重要です。
完成したマウスピースは、患者様の口腔形態に合わせてオーダーメイドで製作されます。装着前には、全体の動き方や最終的な歯並びのイメージを共有し、治療の進行を可視化。こうした工程を丁寧に行うことで、治療中の不安を軽減し、患者様と医師が同じゴールを見据えて進めることができます。
装着〜調整〜完了:すきっ歯が閉じていく過程と保定までの流れ
治療が始まると、1〜2週間ごとにマウスピースを交換しながら、少しずつ歯を理想的な位置へ移動させていきます。定期的な通院では、装着時間の確認や噛み合わせの調整、咀嚼バランスのチェックを行います。治療後には、移動した歯を安定させるためにリテーナー(保定装置)を装着し、後戻りを防止します。
- ・マウスピースの交換(1〜2週間ごと)
- ・装着時間や噛み合わせの確認
- ・リテーナーによる保定と安定化
保定期間は症例によって異なりますが、数か月〜1年ほどかけて歯と骨が新しい位置に馴染むのを見守ります。この時期にも定期的に検診を受けることで、矯正後のかみ合わせや清掃状態を維持でき、長期的に安定した美しい歯並びを保つことができます。矯正は「装着して終わり」ではなく、治療後の管理までが重要なプロセスです。
マウスピース矯正で失敗しないために──ありがちな落とし穴と回避策

装着時間が足りないと動かない?治療中の注意ポイント
マウスピース矯正で最も大切なのは「装着時間の管理」です。一般的に1日20〜22時間の装着が必要とされ、これを守らないと歯が想定通りに動かず、治療期間が延びる可能性があります。食事や会話の際に取り外す時間が長くなると、歯の移動が追いつかず、次のステップのマウスピースが合わなくなることもあります。こうしたズレは微小でも蓄積し、全体の治療精度に影響します。
また、自己判断で装着時間を減らしたり、指示通りに交換しなかったりすると、歯の動きが計画からずれてしまう場合があります。そのため、定期的に歯科医師のチェックを受け、必要に応じてアライナーを再設計することが重要です。
マウスピース矯正は、患者の自己管理と歯科医のサポートが連動することで初めて成果を上げられる治療といえます。自分自身の生活リズムを理解し、無理なく続けられる管理習慣を整えることが成功への近道です。
舌癖や口呼吸を放置すると再発リスクが高まる理由
すきっ歯や歯並びの乱れは、歯だけの問題ではなく、舌や呼吸の習慣にも影響されます。特に「舌癖(ぜつへき)」は、舌が常に前歯を押す癖を指し、これが原因で前歯が前方に開いてしまうことがあります。矯正治療で歯を動かしても、舌の動きが改善されなければ、再び歯が前方へ押し出され“後戻り”が生じることがあります。
また、口呼吸の習慣があると、口腔内が乾燥しやすくなり、頬や舌の筋肉のバランスが崩れて歯列が不安定になります。治療を長持ちさせるためには、マウスピース矯正と並行して「MFT(口腔筋機能療法)」などのトレーニングを取り入れることが有効です。舌の位置や鼻呼吸の習慣を整えることで、治療後の歯並びを安定させ、再発を防ぎやすくなります。
保定(リテーナー)を怠らないことが“成功の鍵”になる
矯正治療後の歯は、移動したばかりで骨や歯ぐきの支持がまだ安定していません。そのままにしておくと、歯が元の位置へ戻ろうとする「後戻り」が起きることがあります。これを防ぐために使用するのが、治療後の“リテーナー(保定装置)”です。
保定期間は、治療と同程度、あるいはそれ以上に重要です。多くの場合、治療直後の数か月は終日装着が推奨され、その後は夜間のみ装着する形へ移行します。リテーナーを怠ると、せっかく整えた歯列がわずかに動き、噛み合わせや見た目に影響することもあります。
また、装置を清潔に保つことや、定期的な点検を受けることも大切です。マウスピース矯正は「動かす治療」と「保つ治療」がセットで初めて完結します。最後までしっかり保定を続けることが、長期的に安定した美しい歯並びを維持する最も確実な方法です。
信頼できる歯科医院を見極めるポイント──診断・適応・アフターケアを比較

原因を見極める“精密診断”ができるかが成否を分ける
マウスピース矯正やインプラント治療など、歯を動かしたり噛み合わせを再構築する治療では、最初の「診断の精度」が結果を大きく左右します。歯列や骨の状態、咬合のバランスを正確に分析できなければ、治療後に「噛めない」「ズレた」といった不具合が生じることもあります。CT撮影や3Dスキャナーを用いた精密診断は、歯の位置や角度、骨の厚み、神経や上顎洞との位置関係を可視化できるため、治療の適応を見極めるうえで欠かせません。
また、画像や模型を患者自身に見せながら説明してくれる医院であれば、自分の口の状態を客観的に理解でき、治療への不安が軽減されます。経験豊富な歯科医師による診断は、単に「できる・できない」を判断するだけでなく、「どうすれば安全に進められるか」を導き出すプロセスです。初回のカウンセリングで丁寧に時間をかけてくれる医院ほど、信頼性の高い治療計画を立てられるといえます。
治療方針・費用を明確に説明してくれる医院を選ぶ
信頼できる歯科医院は、治療の流れや期間、費用を事前に具体的に説明してくれます。インプラントや矯正治療のように複数の選択肢がある場合、治療方法の違いやリスク、治療後の維持管理まで包み隠さず伝えてくれる姿勢が重要です。特に、患者の年齢・生活習慣・希望する見た目などを考慮した上で、「どの方法が現実的か」を一緒に検討してくれるかどうかは医院選びの大きなポイントです。
治療費を分割払い・医療ローンなどで柔軟に対応している医院もありますが、大切なのは金額の安さではなく、費用の内訳や保証内容が明確であることです。納得できるまで説明を受け、メリット・デメリットの両面を理解したうえで治療を始めることが、安心して長く通うための第一歩になります。
矯正後も安心できるアフターケア・保定体制を確認
治療が終わった後のフォロー体制は、長期的に噛める口腔環境を維持するうえで欠かせません。マウスピース矯正では、リテーナー(保定装置)をどのように管理し、どのくらいの期間装着するのかが再発防止の鍵になります。インプラントの場合は、定期的な咀嚼チェックや噛み合わせの確認、周囲の歯ぐきや骨の状態の観察が必要です。治療後の経過観察を怠ると、わずかな歯の移動や噛み合わせの変化が全体のバランスに影響することがあります。
治療後も定期検診やクリーニングを行い、必要に応じて微調整を提案してくれる医院は、長期的に信頼できるパートナーといえるでしょう。単に「治療を終える」ではなく、「その後も健康な状態を保つためのサポート」を提供してくれる医院を選ぶことが、後悔しない治療選択につながります。
歯を削らず、美しく整える──すきっ歯治療の新しい選択肢

“削らない矯正”が注目される理由とメリット
従来、すきっ歯の改善といえば「歯を削って被せる」治療が主流でしたが、近年は歯を削らず“動かして整える”方法を選ぶ方が増えています。削らないことで神経や歯質へのダメージを抑えられ、将来的な再治療や知覚過敏のリスクを低減できる点が大きな利点です。
マウスピース矯正では透明な装置を用いるため見た目への影響も少なく、装着中も自然な印象を保てます。また、食事や歯みがきの際には取り外せるため、従来の矯正装置よりも清潔を保ちやすいのも特徴です。
単に「見た目を整える」だけでなく、歯の寿命を守るという長期的視点からも、削らない矯正は大切な選択肢のひとつといえます。こうした保存的なアプローチは、健康な歯をできるだけ残したいという患者の希望に寄り添う治療として注目されています。
歯を守りながら自然な美しさを取り戻す考え方
削らない矯正の根底には、「美しさは健康な歯の上に成り立つ」という考え方があります。歯を削って形を整える方法は、短期的な仕上がりには優れますが、歯質の減少や将来的な変色、割れやすさといったリスクを伴うこともあります。マウスピース矯正では、天然の歯の形や色を保ちながら、すき間や歯列のズレを無理なく整えられます。
また、歯が正しい位置に並ぶことで、ブラッシングがしやすくなり、歯ぐきの健康維持にもつながります。治療後にホワイトニングを併用することで、人工的ではない自然な白さを引き出せる点も魅力です。見た目の変化だけでなく、口全体の調和と清潔感を育むことが、削らない審美治療の本質といえるでしょう。
まずは専門家に相談して「自分の歯が動くか」を確かめよう
すきっ歯のすべてがマウスピース矯正で対応できるわけではありません。歯の位置関係や噛み合わせ、骨格的な要因によっては、部分的にワイヤー矯正や補綴治療を組み合わせることもあります。そのため、まずは歯科医師による精密な診査・診断を受け、現在の口腔内の状態を正確に把握することが重要です。
専門家による診断では、CT撮影や口腔内スキャンを通して歯の動きやすさを評価し、治療の可否や期間、費用の目安を説明してもらえます。カウンセリングでは不安や希望をしっかり伝えることで、無理のない治療計画を立てることができます。焦らず段階を踏むことで、歯を守りながら美しい笑顔を実現するための最適な道筋が見えてきます。
よくある質問Q&A──“削らないすきっ歯矯正”のリアルを徹底解説

すき間が広くてもマウスピースで治せる?
すき間の広さや歯の傾き方によって治療法は異なりますが、軽度から中等度のすきっ歯であれば、マウスピース矯正での改善が期待できます。マウスピース矯正は歯を削らず、計画的に弱い力をかけながら少しずつ歯を動かすことで、自然に隙間を閉じていく仕組みです。歯質を残したまま見た目を整えられるため、将来的に再治療のリスクを抑えられる点も利点です。
ただし、隙間が大きい場合や全体の歯列バランスに問題があるケースでは、矯正単独での改善に限界があるため、補綴治療(ラミネートベニアなど)を併用することもあります。どの方法が自分に合うかは、精密検査とカウンセリングを通して歯の動き方や骨の状態を見極めることが大切です。
舌癖があっても再発しない?
舌で前歯を押す「舌突出癖」は、すきっ歯の原因や再発の大きな要因になります。矯正で一度すき間を閉じても、舌の動かし方や飲み込み方の癖が残っていると、歯が再び前方に押されて後戻りを起こすことがあります。そのため、矯正治療と並行して舌の位置や嚥下のトレーニング(MFT:口腔筋機能療法)を行うことが非常に重要です。
マウスピース矯正は装置の取り外しが可能なため、トレーニングと併用しやすく、日常生活の中で癖の改善を意識しやすい治療法でもあります。治療後も一定期間はリテーナー(保定装置)を装着し、定期的なチェックを受けることで、歯列の安定と再発防止を図ることができます。
年齢制限はある?何歳からでもできる?
マウスピース矯正は、歯と歯ぐきが健康であれば、年齢を問わず行うことができます。中高生の成長期から、40〜60代の成人まで幅広く適応します。大切なのは「年齢」よりも「歯の支えとなる骨や歯ぐきの状態」です。骨密度が十分で、歯周病などの炎症がコントロールされていれば、高齢でも治療は可能です。
また、インプラントや被せ物がある場合も、周囲の歯が動かせる状態であれば部分的なマウスピース矯正を組み合わせることもあります。治療前には必ずCTなどによる骨の評価と、噛み合わせ全体のバランス確認が必要です。これらを丁寧に行うことで、安全かつ現実的な治療計画を立てることができます。
寝るときだけ装着しても効果はある?
マウスピース矯正は、1日20時間以上の装着が基本条件です。就寝時だけの装着では、歯に加わる時間的な刺激が足りず、思うように歯が動かないだけでなく、治療期間が大幅に延びてしまうことがあります。
理想は、食事と歯みがきのとき以外は常に装着することです。どうしても日中の装着が難しい場合は、治療計画を調整し、進行をモニタリングしながら対応します。装着時間を守ることは、矯正をスムーズに進め、理想の歯並びを実現するための基本です。生活スタイルに合わせたサポートを受けながら、無理のない範囲で続けることが成功のポイントです。
美しさの秘訣は前歯から
東京都の可能な限り削らない審美歯科専門外来
医療法人社団 栄潤会
■LaLaテラス歯科クリニック南千住
住所:〒116-0003 東京都荒川区南千住4-7-2 LaLaテラス南千住2F
TEL:03-3805-4618
■ロイヤルデンタルクリニック南千住
住所:〒116-0003 東京都荒川区南千住4-1-3-2F
TEL:03-6806-8484
■勝どき晴海トリトン歯科クリニック
住所:〒104-0053 東京都中央区晴海1-8-16 晴海トリトン3F
TEL:03-3533-4646
■天王洲シーフォート歯科クリニック
住所:〒140-0002 東京都品川区東品川2-3-10 シーフォートスクエア2F
TEL:03-5783-0118
===監修者紹介===
医療法人社団栄潤会 理事長
高山 剛栄
略歴
日本歯科大学 卒業
ニューヨーク大学 インプラント卒後研修プログラム 卒業
コロンビア大学 インプラント卒後研修プログラム 卒業
医療法人社団栄潤会 理事長
所属学会・認定医・資格
ICOI 国際口腔インプラント学会 日本支部 副会長
ICOI 国際口腔インプラント学会 指導医 認定医
厚生労働者臨床研修指導医
日本歯周病学会
JAID 理事